ブログ
2021.08.31
2021−夏 BOOK LIST
57年ぶりのTOKYOオリンピックが開催され、感染症は蔓延し、行動は規制され、摩訶不思議な2回めの夏が終わろうとしています。
皆様はいかがお過ごしでいらっしゃいましたか?
私はこの夏も、心を本の世界に遊ばせました。
夏休みの宿題ではありませんが何冊か心に残った本をご紹介します。
今年は、今まであまり興味の持てなかった幕末史を扱った本もリストに入りました。

1)「その後の慶喜」家近吉樹著
これが、おちゃらけた「その後の慶喜ライフ」なのかなーと思いきやぜんぜん違うのである。
大政奉還を成し遂げ、心ならずも朝敵の汚名を被せられた慶喜の長い人生後半戦にスポットを当てた作品で、読了した後には、ため息一つ、そしてすぐにアンナ・シャーマンの「追憶の東京」から上野―最後の将軍の章を再読することとなった。
人生は、終わるまで勝者は誰かわからんーというのがまず心によぎったことであり、慶喜のしたたかさ、さすが徳川260年のしぶとさを目の当たりにしたような気がした。
要するに、慶喜は、自分を追い落とした新政府が作り上げた明治の始まりから終わりまでを見届け、そして自らを葬り去った新政府の面々の生き死にを見届け、その間に名誉も回復し、徳川歴代将軍の誰よりも長生きをしたのである。
静岡時代は、渋沢栄一以外の幕臣とは面会せず、これまた蟄居した先で斬首された小栗忠順とは対象的だ。
小栗は、家族と家臣と大量の荷とともに権田村に移ったが、謀反を起こすやもしれぬと新政府に警戒された。
慶喜は、時制が落ち着いた頃、渋沢栄一とともに「昔夢会筆記―徳川慶喜公回想談」を制作して、そしてその後は渋沢栄一とも会わなくなったという。
慶喜は引退後も、徳川武昭や、大正天皇后、有栖川宮などの人々と交流しながら自転車、写真、刺繍、狩り、最晩年には自動車を楽しんだのだそうだ。
諦念はありつつも、ある幸せな一生だったのではないか。
2)「類」朝井まかて著
朝井まかての本は読んだことがなかった。
「類」は、森類。
森鴎外の末子である。森茉莉、小堀杏奴の弟だ。
ここに感染症が出てきた。百日咳で死にかけた茉莉と死んだ不律だ。
その昔、森茉莉に一時大ハマリしていた時期があった。
文庫本で買うのでは物足りなく、筑摩書房から出ている「森茉莉全集」を揃えて、そこから拾い読みして満足していた。
しかし。
この「類」を読んだ後は、森茉莉の作品を読んで、再確認せずにはいられない。
「クレオの顔」
愛すべき姉弟である。
茉莉の気ままさ、自儘。
そして杏奴の、芸術家気質を備えながら、どこか保守的な思考を抜け出せない生活態度。
そして芸術家にもなりきれず、しかしながら生活一般が芸術的である類。
最後は、妻に「働いてください」と懇願される。
杏奴には筆禍で、姉弟関係を断絶され、自儘で掴みどころのない茉莉に共犯者めいた心持ちで、すがり、頼り、金を借りる。
類の、妻と子どもたちに迷惑をかけっぱなしでいながら、戦時中であっても、どうしても東京に出ると自分だけ喫茶店で珈琲とアイスクリームを食べることをやめられない。
いや、やめられないという発想でなく、類にとっては当然の行為なのである。
類は、パリに絵の勉強に行った。
しかし、生活芸術者である彼がパリで得たものは、身にまとう空気感であり、食であり、少なくとも絵に対する真摯な気持ちではなかったのである。
おそらくパリの空気を身にまとった類は、意外と魅力的な男であったのかもしれない。
そんな体たらくでありつつも、美穂との結婚式は帝国ホテルであげた。
一緒に、昼夜逆転の生活をしていた長女の茉莉。
しかし、茉莉だけはその自堕落な生活を見事に芸術に消化させ、作品の中に花開かせた。
最初は杏奴の作品の影に隠れていたように見えたが、最終的には、森家の兄弟の中で一番の文豪となっていったのだ。
そして類はあくまで生活芸術者として終わる。
いや、彼も書いたのだ。
そしてその内容で、杏奴と断絶することになる。
類にはそれがなぜなのかどうしてもわからない。
暮尾は麻里とその息子の普律の間で、「クレ叔父」といふ愛称で、呼ばれていた。
(「クレオの顔」森茉莉)
「類」、このものがたりは、
生活芸術者であり、それを作品に昇華させた茉莉、
生活芸術者であろうとしたけれど、世間の目、母親、夫に美しい夢物語を見せ続けることに転換した杏奴、
そして生活芸術者であることにしか、その意義がないことを認識し続けていた類、
の人生を苦くえがいたものである。
3)「ミシンの見る夢」ビアンカ・ピッツオルノ
サルデーニャ出身のビアンカ・ピッツオルノは、児童文学の作家としてのほうが有名だと、私のイタリア人の友人から知らされた。
19世紀イタリアの話、おそらくシチリアか南イタリアの話であろう。
お針子である主人公は、家族が全員感染症のコレラで死に、唯一の身寄りである祖母と2人で暮らすことになる。
上流階級の家に奉公として住み込むことはせず、半地下ではあるが少なくとも二人の家であるアパートに暮らしながらお針子をして生計を立てている。
祖母が死に、7歳から針の仕事を祖母から見様見真似で習い始めた主人公は、祖母の後を継ぎ、お針子をしながら生活していくことになる。
家賃を払わない代わりに、アパートの共有部分の掃除をしながら、あちこちの家に呼ばれて仕事をしていく。
故に、「お針子はみた!」状態の家族の秘密をたくさん知ることになるのだ。
パリのプランタンからドレスを注文しているかのように見せかけていた弁護士の家族や、若旦那の私生活の隅々まで面倒を長年に渡って見てきた年寄りの女中、自由を謳歌し、主人公に年金を当てながらも最後は殺されてしまったアメリカ人のキャリアウーマンなどなど、登場人物は多彩である。
主人公の秘めたる恋話も出てくるが、決してハッピーエンドには終わらない。
いわゆる大奥様、とよばれる街の上流婦人が死んだのは104歳の時だったりする。
最後は、突然の大円団という気がしないでもないが、19世紀、マッチョなイタリア社会で、女が一人腕一本でしっかり社会に立っていくというテーマは希望を与えてくれる。(とはいえ、主人公はレイプまがいの目にあい、針で応戦したりもする嫌な場面も出てくる)
この本から感じる、懐かしい南イタリアの匂い。
物語から立ち上がってくる空気や風、光までもが懐かしく、過去に何度か過ごした南イタリアの夏がしみじみ恋しい。
4)「万波を翔る」木内昇著
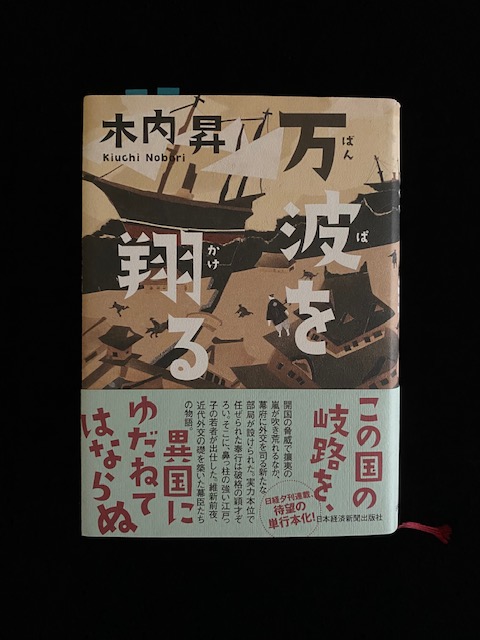
「その後の慶喜」に続く幕末物語。
この本を手にとったのは、大河ドラマの影響にあることは間違いない。おそらく人生で初めてオンタイムで見ている「青天を衝け」
最初は題字が、え、杉本博司なの?程度の興味だった。幕末は明治維新と相まって、日本史の中でも一大転換期であるし、登場人物も沢山いる。
大河ドラマでも何度も取り上げられているこの時代ではあったが、今まではどうも興味を持つことができなかった。
しかし、今回の「青天を衝け」は農民から攘夷活動を経て幕臣に取り上げられ、しかも経済の父とよばれるまでになった渋沢栄一が主人公だし、何しろ脚本が大森美香ということで見ているうちに、だんだんこの時代のことをもっと知りたくなってきた。
大河に続いて、同じNHKの番組で「英雄たちの選択」を見たことも大きかったかもしれない。
その番組では、パリ万博における幕府側の外交失敗が取り上げられていた。
栗本鋤雲、そして田辺太一。
「万波を翔る」の主人公は田辺太一。
1857年、長崎海軍伝習所で学び、後、外国奉行・水野忠徳の下で働くことになる。こうして外交という仕事の末端についた田辺太一は、時制の急な展開とともに、自らも政治と外交の嵐の中に投げ込まれていくというノンフィクションである。
太一はベランメイのチャキチャキ江戸っ子である。
上司におもねることはできない。
思ったことは言う。
だからこそなかなか念願の欧州への使節派遣もかなわない。
二度も行けそうになりつつ、直前でだめになるのだ。
しかし、太一は諦めない。
その後、咸臨丸に乗り、水野とともに小笠原諸島の測量に関わったり、徳川昭武の一行とともにパリの万博にも出向くこととなった。
パリに出向いている間に、徳川慶喜は大政奉還を果たし、田辺の仕事は新政府に受け継がれてしまうことになる。
しかし、ここで田辺は幕府としての今までの外交の失敗点からどうすべきであったのかをまとめた外交指南書を作成し、それを勝海舟に託す。
最後は、渋沢栄一が、沼津の徳川家兵学校の教授におさまった太一を、外務省へ入省させるべく口説きに来るシーンで終わる。
田辺太一は、その後新政府の外務省に入省し、岩倉遣欧使節団に一等書記官として随行、また清国公使館に5年勤務するなど、日本の外交に大きく貢献した。
パリで一緒だった栗本鋤雲は「二君に仕えず」と新政府からの要請を固辞し、その後ジャーナリストとして海外文化を紹介するなど活躍した。
一番の感想が、時代が変わっても国の本質は変わらない、という哀しい感想である。
太一はじめ、彼を取りまく同僚や上司の気質に時代性からくる違和感がない。
昨今の日本の政治の混迷、感染症対策における右往左往、責任の所在のおしつけあい、哀しいほどのリンクを感じるのだ。
もしかしたら岩瀬や、水野のような外からはわかりにくい切れ者、太一のようなパッションだけは誰にも負けないような逸材もいるのであろうか。
(とはいえ、岩瀬も水野も蟄居させられてしまうのだが。。)
しかし、ということはやはり今の時代は混迷を極めた時代だと言うことが言えるのかもしれない。
この国の舵取りをどうしていくのか。
「この国の岐路を異国にゆだねてはならぬ」
5)「ザリガニの鳴くところ」ディーリア・オーエンズ
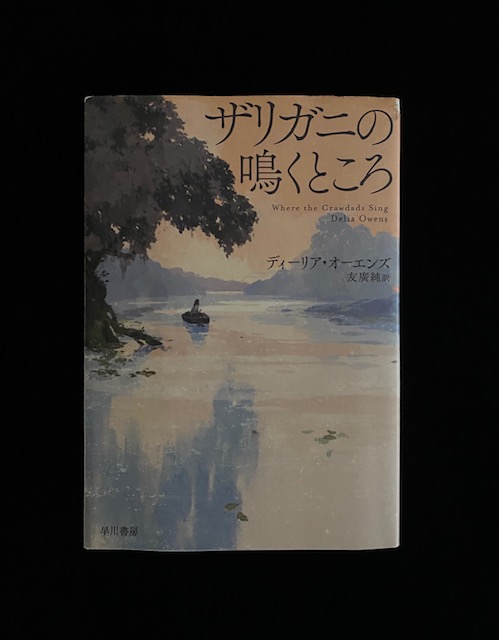
読了後、心は未だ行ったことのないノース・カロライナの湿地をボートでたゆたっている。
昨年からかなり話題になっているミステリー小説である。
ミステリーであると同時に、壮大な女の一生を描いている作品でもある。
作者のディーリア・オーエンズがもともと動物学者であることから、湿地と底に生きる動植物の生態も詳細に描かれており、まるでいつのまにか自分もボートに乗って、湿地のあちこちをさまよっている感覚になるのだ。
幼いカイアのもとからは家族が次々と立ち去った。
まずは3人の兄姉が。
そして母親が。
最後に、一番自分と仲良しだった兄が。
カイアは、アルコール依存症で、暴力的で、人生に絶望している粗野な父親と二人湿地の中の掘っ立て小屋に取り残されたのだ。
しかし嘆いている暇があるわけもなく、なんとか「生き延びる」手段を7歳ながらに講じていかねばならない。
粗野な父親に小銭をもらいながら食料を買い、なんとか料理をして食べていかねばならなかった。
その父親すら失踪してしまった後には、ムール貝を掘り出し、それを黒人の経営する雑貨食料品店に売ることで命をつなぐ。
食料品店の黒人夫妻は、黙ってカイアの手助けをする。
そのうちに、カイアは、後に学者になり、カイアと生涯を共にすることになるテイト、そしてカイアと関係性を持つことになる街の有力者の息子、チェイス・アンドルーズと知り合っていく。
カイアが大人の女性になり、一時付き合いのあったチェイス・アンドルーズが死に、物語は一気にミステリーの様相になっていき、裁判の詳細なシーンが描かれる。
大人になったカイアはどうなったのか?
彼女はその人生をともに行きた湿地の事を知る大家となったのだ。
まだ幼い頃から集めていた湿地に降り立つ鳥の羽根、そして貝のコレクションはいつの間にか博物館並みのレベルになっていた。
そして絵を書くことを覚えたカイアは、湿地の植物や動物の絵を書いた。
カイアは、湿地に生息する動植物や、貝に関する本を出版することになったのだ。
「好き」を追求したら、それが大きく育っていった。
ふと、ちょっと前に読んだ本を思い出した。
「ビシネスパーソンのためのクリエイティブ入門」原野守弘著

名著である。
原野さんは言う。
全ては個人的な「好き」からはじまる。
「好き」とは「共感」し、「連帯」することだ、と。
カイアの「好き」は、テイトの「共感」を生み、出版社の「連帯」により本という形に結実したのである。
作中のアマンダ・ハミルトンの詩も素敵だし、ミステリーの要素にもドキドキしつつ、最終的に、私が一番感動したのがカイアの「好き」が「本」という形に実ることであった。
そして最後は思いがけない展開に、少し心が揺さぶられたのだった。
カテゴリー
最近のブログ記事